映画『オッペンハイマー』考察レビュー
原爆の父が放つ強烈な光と陰
あらすじは?
舞台は第二次世界大戦下のアメリカ。
極秘に立ち上げられた原爆開発プロジェクト“マンハッタン計画”に開発責任者として物理学者のオッペンハイマー(キリアン・マーフィー)が任命される。
オッペンハイマーは生え抜きの科学者たちを率い、原子爆弾を開発する。
1945年8月、日本を降伏に追い込むべく、広島、長崎に原爆が投下される。
苦悩するオッペンハイマー。
戦後、彼を飲み込んだのは、東西冷戦や赤狩りといった時代のうねり、そして軍人政治家ストロースの策謀だった……。
感想1〜なぜ『オッペンハイマー』は「難しい」と言われるのか?
「一発で理解できた人はいるんだろうか?」が一回目感想
「この映画、評判になってるけど、混乱する映画だな〜。気合込めないとついていけないよ…。映画館で観て一回で分かった人、はたしてどれだけいるんだろう??」
これがぼくの1回目に観た時の、正直感想です。
ぼくのIQでは一度で全てをスッキリ理解することは、ぜんぜんできませんでした。
これぞ、良くも悪くも監督クリストファー・ノーラン節です。
「この監督、もうダメ」となるか、「その訳わからなさにハマるんだよねー」となるか、どっちかに振れる監督のように思います。
何かと似てません?
「インド旅」です。
インドも「ハマりまくって何度も行っちゃうヒト」と、「2度と行くもんかあんな国」となるかどちらかだ、なんて聞きますね。それに似てる…と思いました。
クリストファー・ノーランにインドを引き合いに出すなんて乱暴かもしれませんが、それほど強烈な個性が魅力なんだと思います。
「オッペンハイマーの放つ光と陰の話だったのかな..でも難しいよ」が2回目感想
で、ぼくは訳わからなさをかったのが悔しいので2度目を観ました。
言いたいことは、「オッペンハイマーが強烈なオーラを持っていて、その放つ光が濃い影をも作り出していた」…ということね。…と分かったくらい。
明白スッキリという訳じゃなく、なんとなく程度。
正直、時系列を行ったり来たり、登場人物もやたらと多いので、まだ混乱しながら見ていました。
2度目観ても、まだ覚えられない登場人物もいて、自己嫌悪ですよ。
自分のアタマの鈍さに呆れてました。
3度目観て、ようやく理解できた『オッペンハイマー』
2度見してもまだ分かってないぼく…あまりに悔しかったので、3度目観ました。
さすがにようやくスッキリ!です。
『オッペンハイマー』は興行的に大成功した、と聞いてますけど、いや、なんのことはない、実は三分の一の人しか見てなかったりしてね…
ぼくと同じく訳わからなすぎて、でも「わかりませんでした!」って言うのがイヤで、意地で2度3度と通った人が多かったんじゃないか?と、邪推してしまいます。
そんなことないと思いますけど。はい、これはヒガミです。
話戻します。
では、ここから3度見て、ぼくがわかったことを書いてみます。
人それぞれどう見たか?分かったか?って違うと思います。映画はひとつの答えしかない数式とは違いますもんね。
だから、ぼくなりに「見えた」ことを書いておきます。
『オッペンハイマー』はグロい?
感想に入る前に、グロいかどうか?を書いておきます。
原爆の開発投下がテーマになっているわけですから「グロい映画ではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
以下ネタバレです。
原爆投下後の被爆地惨状シーンは出てきません。なので、原爆ワードから想像するような広島長崎の投下後のグロさはなく、…しかし、策謀を巡らす人間の心のグロさはとことん出てくる映画です。
感想2〜わかりにくい構成は三位一体(トリニティ)構成だから?
映画は炎や爆発の印象的な連なりからスタートします。
その火に次のテロップが流れます。
「プロメテウスは神々から火を盗み人類に与えた そのため岩に縛られ永遠に拷問された」
続いてオッペンハイマーがアップで捉えられ「保安聴聞会のみなさま、私に対するあなたの誹謗は、私の人生と仕事の文脈を除いては理解できません」という言葉を口にします。
しかしこの後、映画にいていくのは一苦労となります。
わかりにくい、と思われた方は、以下のような三つの時系列があることを頭に置いて見るとわかりやすいかもしれません。
基本的な内容は、物理学者オッペンハイマーと閣僚将軍ストロースの対立がドラマの大きなテーマとなっています。それを3つの柱で支えています。
その3つの柱とは、以下の3本です。
1・一つは聴聞会です。
オッペンハイマーに対する密室での聴聞会はカラーで表現
2・もうひとつは、公聴会です。
公聴会でのストロースに関わるシーンはモノクローム表現。
3・そして全体に散りばめられるのが、オッペンハイマーの私生活と物理学者としての姿です。
このオッペンハイマーの「私の人生と仕事の文脈」にあたる人生のドラマ部分は、カラーで表現されています。
原爆のテストの作戦名についてオッペンハイマーが「三位一体=トリニティ」と命名する下りが出てくるんですが、映画の作りもまた、三位一体のトリニティを意識しているように思えました。
このトリニティ構成からぼくは、「観客に敢えて考えさせる」クリストファー・ノーランらしさを感じました。
感想3〜日本人として気になる「広島・長崎の描写」はどうだったか
日本人にとって、やはり母国は広島、長崎に原爆を落とされた世界唯一の被曝国ですから、どうしたってその部分がどう描かれるか???そこ、外せないところですよね。
ぼくもそう思って映画に臨みました。前評判であまりその点に触れられていないことは知ってはいましたけど…。それでも、原爆による大量殺戮について、なんらかの言及はあるだろう…と思っていました。
しかし、セリフとしての表現や間接的な暗喩は見つけることはできましたが、残念ながら、クリストファー・ノーラン監督からのメッセージを僕は受け取れなかった…。
確かに、オッペンハイマーの核軍縮への祈りのようなものは描かれていますが、広島、長崎への罪の意識は、映画にはそれほど刷り込まれていないように感じます。
踏み抜いた炭化した物体は何?
1点だけ映画の中でオッペンハイマーが何か「炭の塊のようなものを踏み抜く」シーンがあります。あれはなんだったんだろう?「炭化した人の遺体?かな?」とぼくはとらえましたが、監督の真意はわかりません。
でも炭化した何かを踏み壊しオッペンハイマーが躊躇する演出でしたので、やはり原爆への罪の意識なのではと思っています。(違っていたらごめんなさい)
少なくとも原爆の影響を観客に投げかけた「ヒント」で、意図的な演出であることは間違いないと思います。
しかし、ぼくはやっぱり日本人です。広島長崎についてのメッセージが「うっすら漂っている程度」というのは、どうも納得できなかった…。
映画の中で、木箱に梱包されたリトルボーイ(広島に落とされた原爆のネーミング)とファットマン(長崎に落とされた原爆のネーミング)2発の原爆がトラックに積み込まれ、オッペンハイマーが見送るシーンがあります。
そのシーンも思いっきり思わせぶりなままで、あとはあえて語らずにカットされます。
「問いを投げるのはいいけど、なんか、逃げられたようでズルいよ、、、」
これが広島長崎問題についてのぼくの受けた感想でした。
『オッペンハイマー』考察と解説
「数式に楽譜を見て、その調べを聞け」:ボーア教授
オッペンハイマーは、ゲッティンゲン大ボル教授も元で理論を学びます。その前半ではオッペンハイマーの人間の素地替描かれます。
そこでインサートされるカットが、エリオットの詩を読み、ストラビンスキー春の祭典を聴き、ピカソの半具象絵画へ目覚めるオッペンハイマーの姿です。そして破壊を伴う心の爆発です。
まさしく、これぞ青春。
そんな青春時代、オッペンハイマーはボーア教授からこう言われます。
「数式に楽譜を見て、その調べを聞け」
なんて素敵な言葉だ!
ぼくはそのセリフに鳥肌が立ちました。
だって、ぼく自身芸術の世界に生きていますが、芸術も理系学問も探求していく先に見える光は一緒じゃないかな、、、と薄々思って生きてきましたから。
この、若き日のオッペンハイマーを描くくだりが、僕は、大好きです。
そのシーンの中で笑顔が一瞬だけ現れますがその笑顔以降、オッペンハイマーの純粋な笑顔を見れるカットはなかったと記憶しています。
そこで彼の青春は終わった…のでしょう。
その後、ラビ教授との出会い、彼はカリフォルニア大とバークレーに赴任し、マンハッタン計画へとレールが敷かれていきます。
オッペンハイマーが読んでいたエリオットとは?
T・S・エリオットは、詩人です。当時まったく新しい詩形で英米文学界に大きな影響を与えました。
劇中、若きオッペンハイマーが読んでいる『荒地』(あれち、The Waste Land)は、T・S・エリオットの代表作の長編詩です。世界の混乱と美を同時にえがく作品と評価されました。
都市のイメージ、ジャズのリズムを反響させたその詩は、第一次世界大戦後の新しい感受性のあらわれとして学生や詩人の間で熱狂的に読まれることとなったそうです。
オッペンハイマーとピカソのキュビズム
前半の若きオッペンハイマーが描かれるくだりで、エリオットの本のほかに、当時活躍し出したパブロ・ピカソのキュビズム作品をオッペンハイマーが見るシーンがあります。
キュビズムは今はごく普通に目にしますし教科書にも載っています。しかし第一次世界大戦が終わってまもない頃、その表現はそれまでの表現をぶち壊すものでした。
この一連のシーンは、オッペンハイマーが物理のみならず新しい時代の風を貪欲に理解、吸収しようとしていたことを示した映画表現だったと思います。
子供だった男オッペンハイマー
映画を見ていて感じたのは、オッペンハイマーと言う男は、常に周りから踊らされ、自分が何者なのかがわかっていない、そう、まるで子どものような男だったと感じました。
オッペンハイマーに限ったことではなく、専門を突き詰めていく人間は、多かれ少なかれ子どものような存在なのかもしれません。だから大きなことをなしとげることができる。
1つの街を消し去るような原爆を作るプロジェクトにあっても、やはり成し遂げる人間は、子ども性を持っていたからだろうな….と思います。
戦後、核軍縮や平和を説くオッペンハイマーは、将軍と言っても政治屋のストロースから追い詰められて行きます。
ストロースが仕組んだその仕掛けは二重三重の策が張り巡らされ、彼の前にあっては物理学者オッペンハイマーはまるで赤子です。
ストロースは映画の中でこう言います。「素人は太陽に群れ喰われる。権力とは陰に潜むのだ」と。
国家プロジェクトの中に放り込まれた子供…それ自体が悲劇であり喜劇だな…と僕は感じました。
世界が恐怖を知った時、我々の仕事は人類の平和を確実にする:オッペンハイマー
すべからく政治家は、平和と言うものは幻想であって、平和の裏側には醜い争いがあることを知っている人種でしょう。
国を導いていく人間は、取引、綱引きのバランスの上に生きていかざるを得ません。
「世界が恐怖を知った時、我々の仕事は人類の平和を確実にする」とはオッペンハイマーのセリフですが、政治家は(トルーマン大統領は)多分そんなことを信じてはいません。
でも、物理学者としてのオッペンハイマーは先のセリフを間違いなく信じていたんだと思います。いや、信じたかったのでしょう。
戦後、オッペンハイマーがたどってゆく道筋を見ていると、そんなことを、思わずにはいられませんでした。
我は死なり 世界の破壊者なり
原爆実験のシーンも、爆発カット(キノコ雲が立ち上るような、誰もが想像する絵)で驚かす方法は取らずに、あくまでオッペンハイマーの心の目線で表現していました。
その表現はクリストファー・ノーラン監督が「広島長崎の被害者へどうアピローチするか??」を悩んだ彼なりの答えだったように僕は思いました。
後半、「我は死なり 世界の破壊者なり」というセリフが出てきます。オッペンハイマーの心の目線で表現した爆発シーンカットはそのセリフと一体にように思います。
ギリギリと辛くなるような映画でしたが、オッペンハイマーの味方となるラビ博士の存在は見ている僕にとっても救いでした。
また、同じくオッペンハイマーを擁護するヒル博士の証言も、ストロースの化けの皮を剥がしていく爽快感があり、こちらも救い・その2でした。
アインシュタインがオッペンハイマーを見かねて告げる「私のように、国を捨てろ」という言葉にも、救いを感じました。
祖国を思ってやった結果が祖国から攻められることになったオッペンハイマー。
彼の行動や姿は、国ではなく、組織や学校といったコミュニティに置き換えると、意外や意外、あっちこっちに小さなオッペンハイマーはいそうです。あの映画を見てそんな気がしたのは僕だけでしょうか。
画家として観る「映像美・色彩やそれらの構成」一考察
ぼくはクリストファー・ノーラン監督の持ち味は、考え抜いた分かりにくさにあると思っています。分かりにくいことが悪いことかというと決してそうではありません。
分かりにくかったから僕は3度見返したわけですが、だからと言って映画の質が低レベルかというとそんなことはないわけです。
絵画にしても分かりやすい解説的な絵は、それはそれで機能します。が、アートであるかどうかとは別次元です。
クリストファー・ノーラン監督はVFXを極力使わない監督としても有名です。
『オッペンハイマー』の中でミクロな物理の描写が出てきます。とても美しい表現で、一瞬だけインサートされます。
その描写は、言ってしまえば「何を描いているかわからない描写」でしょう。しかし、観客の意識に突き刺さり「あの映像は何を意味していたんだろう?」と考えさせられます。
観るものの視点を変える美しさこそ、絵画だったり他の芸術の役割なんです。
そう、クリストファー・ノーラン監督はあくまで面倒臭いアナログな技法にこだわることで、観客に考える「間」をさしだしているんです。
この映画の芸術的な面を、さらにもう一つ書いておきましょう。
『オッペンハイマー』では敢えてカラーとモノトーンが使われていますが、僕はモノトーンの表現にカラーシーンとは別の色彩を感じました。
モノクロに色を感じるって矛盾しているように思えますが、決して矛盾はしていません。人は心象として色彩を染め見ることができるのです。色数が限られれば限られるほど、知覚は鋭くなります。人は異質なものに反応します。モノトーンとは異質なものです。なので人はモノトーンに鋭く反応します。異質なものとは、人の想像力を自動的にブーストする添加剤なのです。
説明のためのカットイラストと、観るものに考える余地を与える絵画芸術の間には、大きな違いがあります。そのことを映画に当てはめると分かりやすいでしょう。ノーラン監督は芸術作品として仕上げようと表現しているのだと思います。
僕の評価は?
3度見てようやく全体が掴めた自分の不甲斐なさに呆れています。しかし、映画は分かりにくいからといってマイナスかというとそうではないと思っています。
結果的に僕は脳内のニューロンを総動員し「理解しようと懸命になった」わけで、そう考えると『オッペンハイマー』は「問いの突きつけ方」が素晴らしい芸術的な作品だと僕は感じています。
しかし、「原爆のもたらしたもの」という視点を持ち込むなら、評価は別になってきます。
大量虐殺兵器を使った結果がどうだったのか?その惨状が今の僕らには伝わっています。原爆の父と呼ばれる人物を描く映画を作るのであれば、その点にもっともっと踏み込んでほしかったです。
僕の評価は星三つ半です。
最後に心に刺さってきたセリフを書いておきます。ちなみにこの映画、名言の集まりと言ってもいいくらいに次々と名言セリフが登場するのです。
このブログを読んだ方の『オッペンハイマー』考察への助けになれば…と、以下にいくつか僕の『オッペンハイマーのセリフに見る名言』を書いておきます>(あくまでも、ぼくに突き刺さったセリフですにで、違うよと思う方はスルーしてくださいね)
胸に刺さる『オッペンハイマー』の名言ベスト5
「数式に楽譜を見て、その調べを聞け」=ボーア教授の言葉です
「天才とは紙一重だ。慧眼にして盲目だ」=ストロースの言葉
「時代”が”動かした男」=誰の言葉だったか忘れました…でも、時代”を”動かした、ではない点で強く印象に残っています。
「私のように国を捨てろ」=アインシュタインのオッペンハイマーへのアドバイス。真理を探究することのみに生きた天才物理学者の生き様を、その一言に見せつけられました
「道楽者で女好き、共産主義の疑いあり。情緒不安定で大げさ、尊大で神経質。唯一の長所は、誠実だ」=グローブス大佐が、オッペンハイマーを評した言葉です。
『オッペンハイマー』はどこで観られる?最新の配信・レンタル情報
-
U-NEXT:配信あり(見放題)
-
Amazon Prime Video:レンタル・購入可
-
TELASA:レンタル・購入可
-
Lemino:購入
- Jcom Stream:レンタル・購入可
- TSUTAYA DISCUS:レンタル

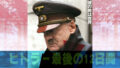

コメント
なかなかムズい映画でした。
私はブログを書くわけではないので、わからんとこはスルーしましたが、
シナリオの構造が錯綜してわかりにくい。
登場人物が多くてわかりにくい。
基礎知識が乏しいのでわかりにくい。
という私の無知ゆえの「わかりにくいトリニティ」、あっちゃ。
しかしながら、オッピーのアスペルガー的精神構造や
それゆえに成し遂げた「科学者」としての成功とそのため生まれた忸怩たる思い。
つまりこの映画は、科学者としての好奇心のまま脇目もふらず突き進んだため
現代のプロメテウスになっちゃったオッピーの伝記映画ですね。
反戦映画でも原爆被害をテーマにした映画でもなく・・と私は観たのですが。
えんえんと描かれる、
科学者(or技術者)と軍人、政治家、ビジネスパーソンとの乖離は
戦時中はどこでもあったことでしょう。
戦艦大和を建造した日本でもね。
そして、今もあるのでしょう、きっと。
米とありがとうございます。ぼくもこの映画は反戦映画や原爆被害の映画ではなく、個人にフォーカスした映画と感じました。現代のプロメテウスとは、言い得て妙です。歴史を見ると、戦争のたびに科学分野や医療分野は飛躍するという事実がありますよね。