『THE DAYS』評価:星五つ
福島原発事故再現実話ドラマ・感想レビュー
誰も知り得なかった福島原発事故の現場が、リアルに描き出されるネットフリックス制作8話連続ドラマが『THE DAYS』です。
吉田昌郎所長役に役所広司、菅直人首相役を小日向文世。他、キャストの力のある静かな演技で、原発事故現場が明かされます。
ぼくは8話連続『THE DAYS』の「続き」を明日に伸ばすことができませんでした。最初に評価を書いておきます。とても良かったです。星五つです。
震災当時、仙台で被災したぼくの家は、電気が止まり、事故情報はラジオのみ……。小さなスピーカーから流れるひどい原発事故情報に、ぼくら家族は固唾を飲んで耳を傾けていました。その100キロ南で繰り広げられていたドラマです。
そんな体験も重ねつつ、実話ベースのドラマ『THE DAYS』のどんなところが良かったのか?見どころ。深読みポイントをレビューしてみます。
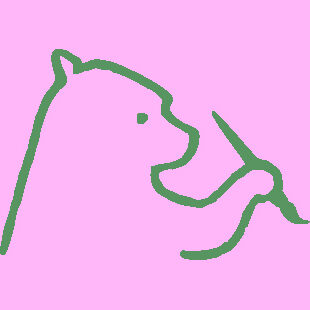
このレビューでわかること↓
『THE DAYS』どこまで実話か?
『THE DAYS』あらすじは?
『THE DAYS』見どころは?何がすごい?
『THE DAYS』感想
『THE DAYS』海外の評価は?
『THE DAYS』Netflix予告編
『THE DAYS』スタッフ・キャスト
企画脚本制作:増本淳 監督:西浦正記 中田秀夫
キャスト:役所広司 竹野内豊 小日向文世 小林薫 音尾琢真 光石研 遠藤憲一 石田ゆり子 他
2023年 8話連続ドラマ Netflix配信
『THE DAYS』あらすじは?(8話連続ドラマです)
『THE DAYS』はノンフィクションドラマです。
ですので、以下、大雑把にだけあらすじを書きます。
2011年3月11日、大地震が宮城県沖で発生、巨大津波が三陸沿岸部に襲来。
福島県浪江町の福島第1原発も高さ15メートルの津波に飲まれ、原子炉冷却に必要な「電源を喪失」する。
冷却装置が動かなくなった原子炉は化け物だ。メルトダウンに向かって放射能を撒き散らしながら暴走をはじめる。
吉田所長以下、原発の技術者、作業員たちは、限られた時間の中、原子炉メルトダウンを防ぐべく、必死の作業を続ける。
現場とは逆に後手後手に回る、政府と東電幹部。それぞれがそれぞれの思惑を振りかざし、現場発電所員は翻弄される。
ドラマはいままで明らかにされてこなかった、そんな酷い現場を淡々と描いています。
『THE DAYS』はどこまで実話か?
ネット上では『THE DAYSは実話か?』や『どこまでが実話なの?」といったコメントが見られます。
まずはその点を明かしてみたいと思います。
何がベース?登場人物は?
『THE DAYS』は、門田隆将が書いたノンフィクション『死の淵を見た男』と「吉田調書」を元に、虚構を極力排除して作られたといいます。
原作『死の淵を見た男』をぼくは読みましたが、現場関係者に丹念な取材を重ねています。その行間からは、福島原発事故の知られざる現場の実態がリアルに浮かび上がっていました。
そして、現場を指揮した吉田昌郎所長が残した現場記録に「吉田調書」と名付けられた報告書があります。(書籍にはなっていません。)
『THE DAYS』は、『死の淵を見た男』と「吉田調書」を元に、虚構を極力排除して作られたといいます
映画俳優が演じる登場人物は、実際に現場にいた人物です。
しかし実際の人物は登場しません。
映画では俳優がそんな人々を演じます。監督も演出を加えます。
そう言った意味では、「事実に沿って演出を加えて作られたノンフィクションに近いフィクション」でしょう。
『THE DAYS』見どころ解説
吉田昌郎所長役に役所広司、菅直人首相を小日向文世。
福島原発の現場を指揮した、実在の故・吉田昌郎所長役を演ずるのは役所広司です。
原発事故をあつかった映画『フクシマ50』で演じられた吉田所長像とは違った、どちらかというと寡黙なトーンで演じられています。
吉田所長が実際現場でどんな感情の発露をしたのかは、分かりません。
しかし、『THE DAYS』において役所広司が静かに演じた吉田昌郎所長の方が、『フクシマ50』の吉田所長像よりも、悲惨な事故現場を指揮する所長として、迫ってくるものを感じました。
また、実在の菅直人首相を小日向文世が演じています。
首相の傍若無人さを演じきっています。
その傍若無人さには演出もあるかと思いますが、死をかけて放射能を抑え込みにかかる現場とのギャップを、小日向文世が見事に浮き立たせ、さらにドラマを深いものにしていると感じました。
何かを際立たせたいときは反対の何かをイジる。表現の鉄則だと思います。
映像の持ちうる、活字ではなし得なかったパワフル説得力
原作『死の淵を見た男』を読んで、修羅場だったことを知ったつもりになっていたのですが、映像には、活字とは異なる人の視覚に「修羅場」を直接刻み込む、別のチカラがありました。
原子炉暴走を止めるべく、放射線量の限界で人力の作業にあたる発電所員たちは、実在の、地肉が通っている人たちです。
「おい、マジかよ。現場ではそんな状況だったのか…」
動き(映像)ほど説得力を増すものはありません。
『THE DAYS』感想〜ネタバレあり
派手な演出ナシで現場のリアルに迫る
『THE DAYS』では派手な演出を極力控えています。多分、意図的に…だと思います。
たとえば、劇中、自衛隊の出動シーンがあります。
アクション映画なら、その手のシーンは、お決まりの「カッコいい撮り方」というものがありますよね。例えば『トップガン』オープニングを思い出してもらうとわかりやすいです。いくつものアングルで光と影を効果的に用いて複数カットで畳み掛ける…そんなテクニックです。
しかし、この映画では、そんな手法を取っていません。
あくまで淡々と自衛隊の出動を描き出します。それが、逆に、リアリティを押し上げています。
そんな、「あえて抑えた演出」から、ぼくは制作陣の「この映画は記録としても残すべき映画だ」という意思が感じられした。
そして役者もまた、それに応えています。騒がしいオーバーな演技など一切出てきません。
それは、製作陣の「現実に原子炉溶融という恐怖に対峙した男たちへの敬意の表れ」だ、と、とぼくは感じました。
「原発事故対応に必死に当たる原発所員」を描くって、ついついドラマチックに盛り上げたくなるような素材ですよね。
しかしあえてドラマチックにせずに最後まで見せ切ったのは、やはり監督はじめキャストの力技なのだと思います。
『THE DAYS』は究極のホラーだ
『THE DAYS』において、原発所員が電源喪失した真っ暗な原子炉建屋で戦う相手は、「目に見えない放射線」「致死量まで高まった放射能」です。
原発所員は。限られたわずかな時間でバルブを開けるために漆黒の建屋内を手探りで進みます。
『真っ暗闇の中、登場人物が、目に見えない「何か」に襲われる恐怖の中、手探りで前に進む』
↑このシチュエーションは、どんなジャンルの映画でしょう?
そう、ホラー映画です。
1話2話3話…とドラマが進むにつれて、ぼくは正真正銘の「ホラー映画」を観ている気分になってきました。
ホラー映画と違うのは、迫ってくる恐怖を抑え込んで立ち向かう相手が、リアルだったということです。
想像してみてください。暗闇の中を進む防護マスクの中で聞こえる自分の呼吸音を。
そして漆黒の中、無慈悲にデンジャーソーンを告げ鳴り響く線量計。
懐中電灯だけを頼りに、目に見えない恐怖=放射線=と必死に戦う彼らの精神的恐怖は、いかほどだったでしょうか?
映画では、汗と吐く息で曇り切った防護マスク越しのカットが何度も出てきます。
そのカットもまた、従事した作業員への「よくもそんな極限で作業をしてくれましたね、、、」という、敬意の表れの表現だったと思います。
ぼくらは水蒸気爆発を知ったつもりになっていただけ
震災当時、マスコミが撮った「水蒸気爆発」の映像は世界中を駆け巡りました。
その映像は衝撃的なものでした。
なので、誰もがなんとなく「知ったつもりになっている」のですが、実は誰も「なにも知らなかった」のです。
なにも、って?
それは、
「爆発の直後、現場で当たっていた人々の目線では、どんな惨状だったのか?」です。
『THE DAYS』では、自衛隊員の目線を借りて、爆発当時の修羅場をていねいに描き出していました。
このシーンも必見です。
だって、誰も知ってるつもりになってい見たことがなかった現場を再現しているのですから。
『THE DAYS』ぼくの評価は?
『THE DAYS』を観ていて、ぼくはこう思いました。
「放射能というバケモノクリーチャーを生み出し、襲われ、終わりなき戦いへと突き進んでいる今、結局、日本に生きているぼくら誰もが、恐るべきクリーチャーなのかもな…」
ぼくの究極まとめは、これに尽きます。
そんなまとめをくれた『THE DAYS』、ぼくの評価は星五つです。
ぜひ、一人でも多くの方に見てもらいたいドラマです。
『THE DAYS』海外の評価は?
肯定的な評価
配信初週のNetflixグローバルランキングで「非英語TV」部門5位にランクイン配信直後から高い注目を集めたそうです。
否定的な評価
おまけ:ぼくの実話〜原発事故の時ぼくら家族はどう動いたか
これは『THE DAYS』からちょっと離れまたおまけ記事ですので、興味ない方はスルーしてください。以下は、100キロ離れた仙台でぼくら家族がどう動いたのか?のノンフィクションです。
『THE DAYS』劇中、日本地図がクローズアップされます。
その地図には福島第一原発を円の中心に、北東北から関東一円までがぐるりと囲まれています。
当時、実際に仙台で被災した僕ら家族は、ライフライン寸断、テレビは見られませんでした。
しかし、ラジオの原発事故ニュースを聞きながら、ぼくの頭の中にはまさにその地図がイメージされていました。
行政はもちろん仙台市民に避難の指示は出していません。
しかし、そのイメージを紙にざっと描いたぼくは「これはやばい。仙台はアウトだ。実家のある盛岡まで避難しよう」と思いました。
なぜぼくがそう思ったのか?それは過去のチェルノブイリ原発事故があったときに原発関連本を読みあさっていたからです。
それら関連本に書かれていた断片が記憶の底から急浮上してきました。
「放射能被害は現場に限ったことではないよ」と、浮かび上がった記憶の断片はぼくに訴えました。
結果、家族で話し合い、最低限の荷物を車に詰め込み、残り少ないガソリンを気にしながら北へ向かいました。
以下、その時の教訓です。
『逃げるか残るか?決めるのは、行政やマスコミではない。自分たちだ。』
原発事故のみならず、自然災害大国となっている日本。
いざという時の決定は、自分たちです。
『THE DAYS』を観ながら、そんな体験を思い出していました。
『THE DAYS』歴史の記録としての映画の役割
ぼくの弟は、その昔、とある映画学校で映画作りを学びました。
先日久々に彼と会って映画談義となりました。
会話の流れで、彼は言いました。
「映画には歴史上の事件を記録す役割があるんだ。
アメリカではウォーターゲート事件や、9.11の後にすぐに映画が作られたよね。
アメリカの映画界には、そんな役割認識があるんだよね。
日本でも大事件を取り上げた映画、あることはあるけど、そんなに多くはないでしょう?
残念だけど、日本は遅れをとっているかもしれない。」
なるほど、と、思いました。
この映画はまさに、「負の歴史の記録」でした。
8話連続ドラマで配信のスタイルをとりましたが、日本の映画史にも刻まれる一本だと思います。
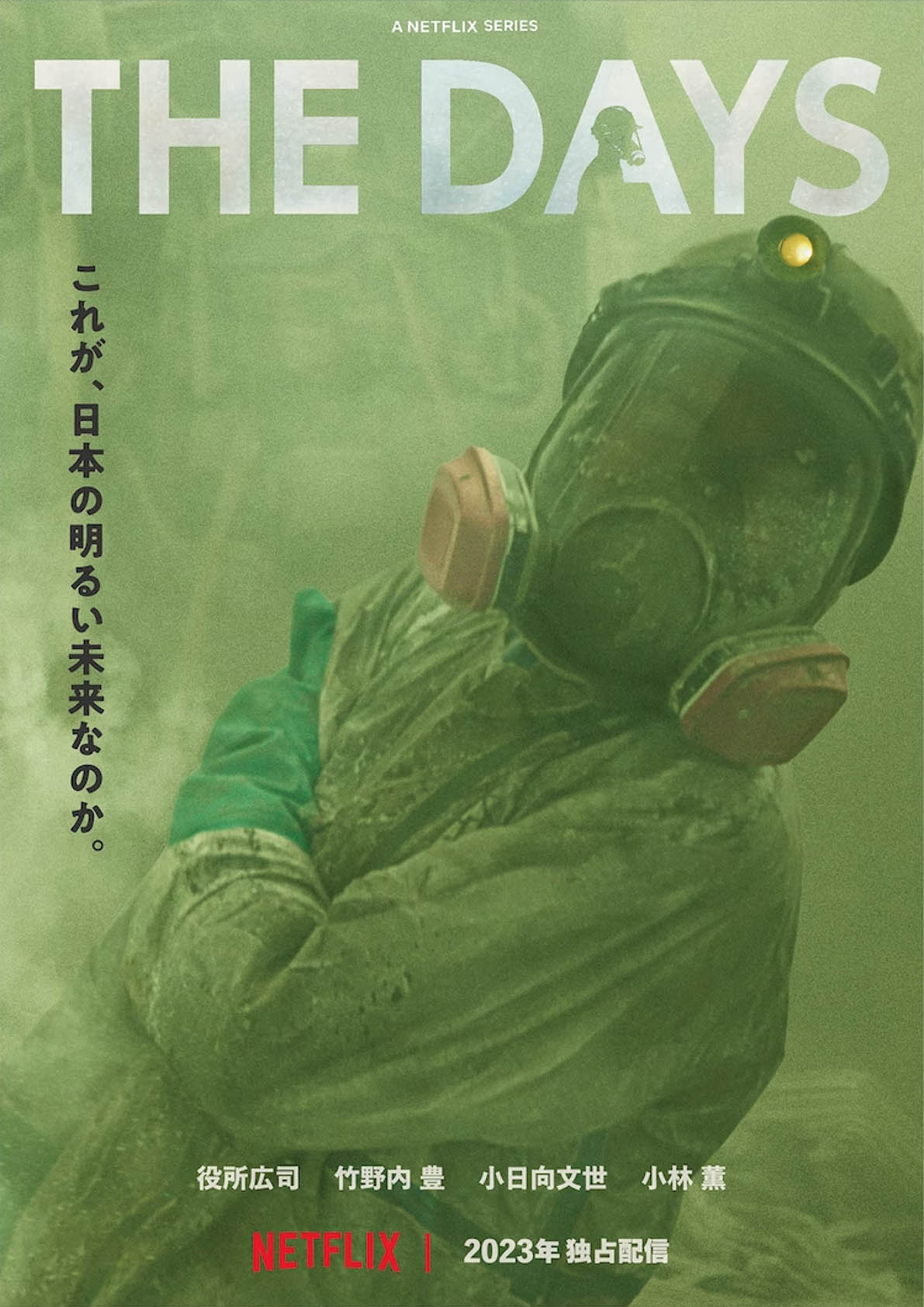



コメント